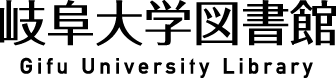今西錦司氏旧蔵抜刷(さ行)
さ
| 読み | 著者名 | 標題 | 和洋 | 配列番号 |
|---|---|---|---|---|
| さか | 酒井 敏明 | ヒマラヤを越えた日本人(二) | 1627 | |
| 酒井 敏明 | ヒマラヤを越えた日本人(三) | 1628 | ||
| 酒井 敏明 | ヒマラヤを越えた日本人(一) | 1629 | ||
| 坂上 昭一 | Some bees of apinae and xylocopinae collected in Canbodia | Y | 19 | |
| 坂上 昭一 | Arbeitsteilung der arbeiterinnen in einen zwergvolk, bestehend aus gleichaltrigen volksgenossen | Y | 205 | |
| 坂上 昭一 | A new ethospecies of stenogaster wasps from Sarawak, with a comment on the value of ethological characters in animal taxonomy | Y | 287 | |
| 坂上 昭一 | Female dimorphism in a social halictine bee, halictus (seladonia) aerarius (smith) (hymenoptera, apoidea) | Y | 332 | |
| 坂上 昭一 | Ethological peculiaritiesnofnthe primitive social bees allodape lepeltier and allied genera (1) | Y | 333 | |
| 坂上 昭一 | An ecological perspective of marcus island, with special reference to land animals | Y | 334 | |
| 坂上 昭一 | The false-queen: fourth adjustive response in dequeened honeybee colonies | Y | 335 | |
| 坂上 昭一 | A bumblebee thieving from a honeybee hive | Y | 336 | |
| 坂上 昭一 | Bees of xylocopinae and apinae collected by the Osaka city university biological expedition to southeast | Y | 337 | |
| 坂上 昭一 | Ueber scatella calida Matsumura, eine Japanischen heissen quellen bewohnenden fliegenart (diptera, ephydridae) | Y | 338 | |
| 坂上 昭一 | An attempt to rear the Japanese bee in a framed hive (studies on the Japanese honeubee, apis cerana cerana fabr, IV) | Y | 339 | |
| 坂上 昭一 | Work efficiency in heterospecific and froups composed of hosts and their labour parasites | Y | 340 | |
| 坂上 昭一 | Some biological observations on a hornet | Y | 342 | |
| 坂上 昭一 | Some interspecific relations between Japanese and Europian honeybees | Y | 417 | |
| 坂上 昭一 | 南十字星のもとで | 434 | ||
| 坂上 昭一 | ハリナシハナバチの生態とその飼養化(2) | 573 | ||
| 坂上 昭一 | ハリナシハナバチの生態とその飼養化(1) | 574 | ||
| 坂上 昭一 | ミツバチの巣面利用にみられる規則性 | 575 | ||
| 坂上 昭一 | 然別湖附近におけるナキウサギの生態に関する2,3の観察 | 578 | ||
| 坂上 昭一 | カイネコの行動圏に関する小調査 | 579 | ||
| 坂上 昭一 | アカヤマアリによるドイツの森林保護 | 590 | ||
| 坂上 昭一 | HedigerのBiologische Rangordnung(同位種間順位態)について | 913 | ||
| 坂上 昭一 | ハナバチ類の比較社会学 II | 1313 | ||
| 阪本 寧男 | 考古学的に見た栽培コムギと栽培オオムギの起源 | 1122 | ||
| 阪本 寧男 | アビシニア高原栽培植物採集の旅 | 1131 | ||
| さき | 崎田 龍二 | 立山御前澤の谷頭に横はれる氷塊に就て | 526 | |
| さく | 佐久間 惇一 | 五頭山をめぐる信仰 | 736 | |
| 佐久間 惇一 | 信仰伝承 | 737 | ||
| 佐久間 惇一 | 水運 | 920 | ||
| ささ | 佐々 保雄 | 氷河問題 | 115 | |
| 佐々 保雄 | 昭和9年度に於ける本邦氷河問題の展望 | 116 | ||
| 佐々 保雄 | 樺太散江郡野頃産マンモスElephas primigenius (blum.)歯化石に就いて | 197 | ||
| 佐々 保雄 | 南樺太東北部沿岸地域の地質に就いて | 198 | ||
| 佐々 保雄 | 千島列島関係文献表 | 290 | ||
| 佐々 保雄 | 色丹島の地質及地形 | 322 | ||
| 佐々 保雄 | 積雪期の大雪山彙 | 444 | ||
| 佐々 保雄 | アラスカの石炭と石油 | 1249 | ||
| 佐々 保雄 | アリウシャン列島と其の地質及び鉱床 | 1250 | ||
| 佐々 保雄 | 山の地質学 | 1615 | ||
| 佐々 保雄 | 日高山脈:その生い立ち | 1626 | ||
| 佐々木 高明 | 焼畑農業の研究とその課題 | 167 | ||
| 佐々木 高明 | 南米における焼畑農業についての二三の考察 | 269 | ||
| 佐々木 高明 | パーリア族調査記(五) | 457 | ||
| 佐々木 高明 | パーリア族調査記 | 458 | ||
| 佐々木 高明 | パーリア族調査記(三) | 459 | ||
| 佐々木 高明 | パーリア族調査記 | 460 | ||
| 佐々木 高明 | パーリア族調査記(一) | 461 | ||
| 佐々木 高明 | わが国における焼畑の地域的分布 | 533 | ||
| 佐々木 高明 | 南九州山村の焼畑農業経営 | 547 | ||
| 佐々木 高明 | 焼畑におけるイモ栽培についての覚書 | 561 | ||
| 佐々木 | Pflanzensoziologische untersuchungen uber buchenwaideer am berg kammuri, provinz Hiroshima | Y | 208 | |
| 笹本 馨 | 梅毛虫蛾卵の寄生蜂の生活史に就て | 1200 | ||
| 笹本 馨 | これからの農業発展の基礎:ミミズの効用と飼育 | 1393 | ||
| さし | 佐治 寺夫 | 人格形成における文化的・社会的要因 | 1427 | |
| さと | 佐藤 月ニ | 備北中国山脈・帝釈峡の動物 | 873 | |
| 佐藤 月ニ | 太田川巣系の魚類とその分布について | 877 | ||
| 佐藤 月ニ | 三段峡・八幡高原の両生類 | 1277 | ||
| 佐藤 月ニ | ヒラタドロムシの成虫と幼虫 | 1278 | ||
| 佐藤 月ニ | 比婆山産タカチホヘビ | 1281 | ||
| 佐藤 月ニ | 三段峡汚染流水の回復に伴う水生昆虫の遷移 | 1506 | ||
| 佐藤 治雄 | 斜面の植物生産量 | 631 | ||
| さわ | 沢井 芳男 | マレーシアの毒蛇 | 1570 | |
| 澤本 孝久 | ヒメギフテフの産卵に就いて | 1202 | ||
| 椹木 道次郎 | 日本産蚊科目録 | 400 |
し
| 読み | 著者名 | 標題 | 和洋 | 配列番号 |
|---|---|---|---|---|
| しか | 志賀 金伍 | 独占期のイギリス貨幣市場と資本市場 | 542 | |
| 志賀 金伍 | 独占期のマーチャント・バンカー | 544 | ||
| 志賀 金伍 | イギリス金融資本分析の一視角 | 656 | ||
| 志賀 金伍 | 独占期のイギリス発行商会 | 657 | ||
| 志賀 金伍 | 独占期のイギリス発行市場を構成する金融機関 | 658 | ||
| 志賀 金伍 | イギリス海外投資序論 | 659 | ||
| 四方 治五郎 | 植物種子発芽の際の酵素の生成とジベレリン | 1406 | ||
| しけ | 資源科学諸学会連盟 | 内蒙古渾善達克砂丘地帯の学術調査 | 504 | |
| した | 志田,順 | 機構の永年変化と東亜諸勢力の興亡盛衰 | 1343 | |
| しの | 篠田 統 | 士族屋敷 | 134 | |
| 篠田 統 | 西日本の酒造杜氏集団 | 997 | ||
| しは | 芝 丞 | 気候と性格 | 173 | |
| 柴田 喜久雄 | 潜土棲昆虫の生態学的研究(一) | 1194 | ||
| 柴田 喜久雄 | 潜土棲昆虫の生態学的研究 | 1213 | ||
| 柴谷 篤弘 | 棲みわけをどう考えるか | 1511 | ||
| 渋谷 寿夫 | サメシマチビアナバチPsen (mimumesa) sameshimai (yasumatsu) の習性 | 14 | ||
| 渋谷 寿夫 | ヌカダカアナバチ(Tachysphex Japonicus Iwate)の生態に就いて | 215 | ||
| しま | 島, 五郎 | ポリネシア人の体質人類学的研究 | 939 | |
| 島, 五郎 | Uber das hautleistensystem der finger und zehennbeeren der Polynesier und der gemischten Polynesier | Y | 262 | |
| 島, 五郎 | Problems of race formation of the maori and moriori in terms of skulls | Y | 263 | |
| 島津 | 群馬県温川における放流アユの漁獲率について | 1226 | ||
| しみ | 清水 義孝 | 三重県員弁川の魚類相と分布 | 1440 | |
| しろ | 城 五郎 | 川の魚の生活 | 812 | |
| しよ | 正垣,幸男 | ネパールに於けるマラリア及びハマダラカに関する研究 | 1302 | |
| 庄司 吉之助 | 「会津農書付録」に現れた会津地方の農業 | 1609 | ||
| 荘田 幹夫 | An experimental study on dynamics of avalanching snow | Y | 148 | |
| 荘田 幹夫 | 最近のなだれの研究 | 1127 | ||
| 荘田 幹夫 | 表層なだれの発生条件 | 1128 | ||
| 荘田 幹夫 | なだれの囁き | 1129 | ||
| 荘田 幹夫 | なだれの話 | 1130 | ||
| 荘田 幹夫 | 3:なだれの研究の傾向 | 1528 | ||
| しろ | 白石, 芳一 | ワカサギの標識放流 | 991 | |
| 白石, 芳一 | 人工湖相模湖の陸水学的研究(1949-1950) | 1179 | ||
| 白鳥 芳郎 | Ethnic configurations in sourthern China | Y | 290 | |
| 白水 隆 | Some new formosan butterflies | Y | 89 | |
| 白水 隆 | New or little known butterflies from the north-eastern Asia, with some synonymic notes ii | Y | 202 | |
| 白水 隆 | New or little known butterflies from the north-eastern Asia, with some synonymic notes iii | Y | 206 | |
| 白水 隆 | Morphology of the male genital organ of argyronome laodice Japonica menetries | Y | 209 | |
| 白水 隆 | chrysomelid-beetles from the Tsushima islands, Japan | Y | 210 | |
| 白水 隆 | Three new species of the angulosa- group of the genus dactylispa weise from Japan, Manchuria and formosa | Y | 211 | |
| 白水 隆 | A new pithecops from the Tsushima islands, Japan | Y | 212 | |
| 白水 隆 | Two new subspecies of erebia niphonica janson from Honshu, Japan | Y | 213 | |
| 白水 隆 | An unrecorded thecline butterfly from formosa | Y | 214 | |
| 白水 隆 | 日本のファウナに新しく加えられるセセリチョウ科の1種について | 589 | ||
| 白水 隆 | 紅頭嶼より発見されたキシタシロチョウ(新称)について | 616 | ||
| 白水 隆 | 台湾産euthalia属タテハチョウの1新種 | 617 | ||
| 白水 隆 | 分布ご種の問題 | 977 | ||
| 白水 隆 | 三徳山における森林植生の植物群楽生態学的研究 | 977 | ||
| 白水 隆 | 蝶類雑記(1-5) | 992 | ||
| 白水 隆 | 日本におけるホシボシキチョウの発見 | 993 | ||
| 白水 隆 | 奄美大島産テングチョウの一新亜種 | 994 | ||
| 白水 隆 | 日本におけるタッパンルリシジミの発見 | 995 | ||
| 白水 隆 | ウライクロシジミの対馬における発見 | 996 | ||
| 白水 隆 | 山形県産チョウセンアカシジミの1新亜種 | 1284 | ||
| 白水 隆 | 琉球八重山群島産セセリチョウ科の2種について | 1290 | ||
| 白水 隆 | 台湾産アゲハチョウ科の1未記録種 | 1294 | ||
| 白水 隆 | 松虫:従来の日本蝶相の生物地理的kね旧方法の批判及びその構成分子たる西部支那系要性に就いて | 1424 | ||
| 白鳥 芳郎 | 民族系譜から見た華南史の構成試論 | 513 | ||
| しん | 信州ローム研究会 | 野尻湖底の第一次発掘調査報告 | 1540 | |
| 神保 | Pollen=analytical studies of peat formed on volcanic ash | Y | 221 | |
| 新保 友之 | ニジュウヤホシテントウとオオニジュウヤホシテントウの分布限界指標の列島分布への適用 | 1389 | ||
| 新保 友之 | 伊吹型コブオオニジュウテントウと列島地史 | 1390 |
す
| 読み | 著者名 | 標題 | 和洋 | 配列番号 |
|---|---|---|---|---|
| すか | 菅野 新一 | 山村で聞いた話(四) | 452 | |
| 菅野 新一 | 新地の仕送り制度と仕送り台帳 | 464 | ||
| 菅野 新一 | 蔵王山のけもの | 559 | ||
| 菅野 新一 | 蔵王山のカモシカ | 565 | ||
| 菅野 新一 | うそこじ三人男 | 1596 | ||
| 菅野 新一 | わすの命は惜すぐねエ | 1605 | ||
| すき | 杉浦 邦彦 | 平倉演習林の鳥類とその生息状況について | 612 | |
| 杉山 幸丸 | The ecology of the lion-tailes macaque [macaca silenus (linnaeus)]-a pilot study | Y | 429 | |
| 杉山 幸丸 | 霊長類の社会の比較 | 690 | ||
| 杉山 幸丸 | ハヌマン・ラングールの社会生態(予報) | 974 | ||
| 杉山 幸丸 | 霊長類の適応と社会構造 | 1488 | ||
| すす | 鈴鹿,紀 | 珍しい植物 | 1340 | |
| 鈴鹿,紀 | 東部地中海沿岸の植物 | 1512 | ||
| 鈴木, 秀夫 | 低位周氷河現象の何軒と最終氷期の気候区界 | 984 | ||
| 鈴木 時夫 | 白山南龍馬場湿原の植生と生態 | 1064 | ||
| 鈴木, 秀夫 | 日本の気候区分 | 1100 | ||
| 鈴木 晃 | 霊長類学の成立と人類起源論 | 1595 | ||
| 鈴木 時夫 | Entdeckung eines pleistozanen hominiden humerus in zentral-Japan | Y | 152 | |
| 鈴木 時夫 | Communications of vii international congress of anthropological and ethnological sciences Moscou, August 3-10, 1964 | Y | 184 | |
| 鈴木 時夫 | forest and bog vegetation within Ozegahara basin | Y | 204 | |
| 鈴木 時夫 | schneetalchen-gesellschaften des gassan-gebirges in Japan | Y | 261 | |
| 鈴木 時夫 | 奥黒部地方の高山および亜高山植生の植物社会学的研究 | 730 | ||
| 鈴木 時夫 | 奥黒部の亜高山帯森林植生 | 731 | ||
| 鈴木 時夫 | 高崎山野生ニホンザル生息地の植物社会 | 732 | ||
| 鈴木 時夫 | 雨乞浜の森林および草原植生における葉のけい酸およびカルシウム量について | 930 | ||
| 鈴木 時夫 | 立山,白山の高山帯高茎草原ホソバトリカブト=タテヤマアザミ群集について | 943 | ||
| 鈴木 時夫 | 尾瀬ヶ原及び周辺の森林及び湿原植生(2) | 990 | ||
| 鈴木 時夫 | 視野の尺度による植物社会の環境の差異 | 998 | ||
| 鈴木 時夫 | 日本の自然林の植物社会学的体系の概観 | 1172 | ||
| 鈴木 時夫 | 中部ならびに東北日本の亜高山帯について | 1426 | ||
| 鈴木 時夫 | 白山の植生分布と垂直植生帯 | 1476 |
せ
| 読み | 著者名 | 標題 | 和洋 | 配列番号 |
|---|---|---|---|---|
| せき | 関口 武 | 日本各地の広域面からの蒸発量の分布 | 28 | |
| 関口 武 | 気候的に見た日本各地の水の過不足 | 29 | ||
| 関口 武 | 気候表現に於ける水分平衡の問題 | 30 | ||
| 関口 武 | 柿の梢の偏向より判断した赤穂扇状地の書架の卓越風 | 145 | ||
| 関口 武 | 卓越風と民家 | 472 | ||
| 関口 喜一 | ミツバチの外役活動に関する研究 | 576 | ||
| 関口 喜一 | 北海道におけるミツバチの花粉荷に関する研究 | 577 | ||
| 関口 喜一 | 寒地における蜜蜂群の越冬に関する研究 | 619 | ||
| 積雪地方農村経済調査所 | 積雪の沈降及び積雪内に於ける鉄棒の曲りに就いて | 176 | ||
| 積雪地方農村経済調査所 | 融雪に関する研究 | 181 | ||
| 積雪地方農村経済調査所 | 積雪地方農村経済調査所概要 | 407 | ||
| 積雪地方農村経済調査所 | 積雪調査要綱 | 439 | ||
| せと | 瀬戸口 烈司 | 哺乳動物の社会進化についての試論:古生物学の立場から | 1554 | |
| せん | 千田 正作 | わが国の家族農業経営における雇用労働とその経営的役割 | 1146 | |
| 仙波 治 | 岐阜県の動物相概説(予報) | 661 | ||
| 仙波 治 | 中部山岳と飛騨高地の自然と動物相 | 1237 | ||
| 仙波 治 | 自然・生物・人の生態系内の調和を指導するにはどうしたらよいか | 1238 | ||
| 仙波 治 | 人間形成の学としての生物学の体系(1) | 1239 | ||
| 仙波 治 | 人間形成の学としての生物学の体系(2) | 1240 | ||
| 仙波 治 | 蚊の習性分布に関する調査と防蚊対策(6)(7) | 1241 |
そ
| 読み | 著者名 | 標題 | 和洋 | 配列番号 |
|---|---|---|---|---|
| そぶ | 祖父江 孝男 | Childhood ceremonies in Japan: regional and local variations | Y | 32 |
| 祖父江 孝男 | ミクロネシアにおけるココヤシ葉製編籠 | 473 | ||
| 祖父江 孝男 | 紀行・風土と民族性・国民性 | 480 | ||
| 祖父江 孝男 | 文化人類学に於けるロールシャッハテスト使用の問題 | 1178 |