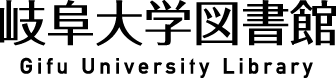今西錦司氏旧蔵抜刷(あ行)
あ
| 読み | 著者名 | 標題 | 和洋 | 配列番号 |
|---|---|---|---|---|
| あい | 相坂 冀一郎 | 嬰児殺しということ(1):人類の繁殖戦略 | 1447 | |
| 相坂 冀一郎 | 嬰児殺しということ(2):人類の繁殖戦略 | 1450 | ||
| 相坂 冀一郎 | ネオテニーということ(2):現代進化論の弱点を補うために | 1451 | ||
| 相坂 冀一郎 | ネオテニーということ(1):現代進化論の弱点を補うために | 1452 | ||
| 会田,雄次 | ルネッサンスの美術と社会 | 1353 | ||
| 相野田 銀司 | 私の得た遺伝と進化論研究の総括 | 1086 | ||
| 相野田 銀司 | 私の得た遺伝と進化論研究の総括 | 1087 | ||
| あえ | 阿江 茂 | A study of hybrids in the papilio machaon group | Y | 442 |
| 阿江 茂 | アゲハチョウ属の種間交配による分類と種の研究 | 66 | ||
| あお | 青木 陽岳 | 地球文明の色分け | 1525 | |
| 青森営林局 | *雪に関する試験報告 | 442 | ||
| あか | 赤沢 威 | Restoration of body size of Jomon shellmond fish | Y | 273 |
| 赤沢 威 | 縄文貝塚産魚類の隊長組成並びにその先史漁労学的意味 | 735 | ||
| 赤平 | Zum gegenwartigen zuchtzustand der Japanischen honigbiene I Kyushu sud-Japan studien zur Japanischen honigbiene | Y | 341 | |
| 赤平 | Notes on the difference in some external characteristics between Japanese and European honey-bees | Y | 349 | |
| あく | 阿久津 昌三 | 国民国家の形成における政治分析の枠組:政治人類学と比較政治学に関する考察 | 1405 | |
| 阿久津 昌三 | アシャンティ族の権力と象徴 | 1415 | ||
| 阿久津 昌三 | アシャンティ族における男性と女性の二元的な象徴分類 | 1574 | ||
| あさ | 浅井 辰郎 | アイスランド全国地誌(4) | 55 | |
| 浅井 辰郎 | 大井川水温の符上観測による諸結果 | 594 | ||
| 浅井 卓夫 | ヒトの白血球 | 833 | ||
| 浅倉 繁春 | サルの繁殖生理に関する研究 | 1121 | ||
| 朝日 稔 | トカラヤギの半野生群における鳴き声 | 131 | ||
| 朝日 稔 | 友が島のタイワンリス | 138 | ||
| 朝日 稔 | 友が島のタイワンリス II | 139 | ||
| 朝日 稔 | 瀬戸内海諸島のシカ II | 140 | ||
| 朝日 稔 | 瀬戸内海諸島のシカ I | 141 | ||
| 朝日 稔 | ツシマヤマネコのスカトロジー | 653 | ||
| 朝日 稔 | 脊椎動物の社会構造 | 733 | ||
| 朝日 稔 | 放し飼いのカイウサギ群の社会生態 | 851 | ||
| 朝日 稔 | 友が島におけるトカラヤギの半野生群 | 1282 | ||
| 朝比奈 英三 | 北海道北見国藻琴沼の貝殻帯 | 15 | ||
| 朝比奈 正二郎 | Odonata-anisoptera of Micronesia | Y | 24 | |
| 朝比奈 正二郎 | 台湾産未記録の蜻蛉類 | 111 | ||
| 朝比奈 正二郎 | 朝鮮半島の蜻蛉相(1) | 112 | ||
| 浅間 一男 | 中生代前期における古生代末植物クの解体とその意義 | 1484 | ||
| 浅間 一男 | ベネチテス類の絶滅と被子植物の出現:恐竜の絶滅に関連して | 1486 | ||
| 浅間 一男 | 古生代末植物区の成立について | 1498 | ||
| 浅見 千鶴子 | Personalityの比較心理学的研究1 | 234 | ||
| あず | 東 滋 | 屋久島原生自然環境保全地域のヤクザルの生態 | 1544 | |
| 東 滋 | クマのセイブツガクと保護に関する現状 | 1582 | ||
| あた | 安立 尚武 | 郡上郡の蛾 | 680 | |
| あつ | 厚田 利勝 | 技術論ノート | 1280 | |
| あべ | 阿部 とし子 | 賃労働者層の存在形態と都市家族の諸類型 | 1221 | |
| あん | 安藤 久次 | 木曽御嶽山における蘚苔植物の群落生態とフロラ | 267 |
い
| 読み | 著者名 | 標題 | 和洋 | 配列番号 |
|---|---|---|---|---|
| いい | 飯島 | Ecology economy and social system in the Nepal Himalayas | Y | 348 |
| 飯島 衛 | 形態学の基礎理論 | 1208 | ||
| 飯島 衛 | 桑田義備とその周辺と私 その4:生命哲学の形成 | 1551 | ||
| 飯塚 浩二 | 戦争末期における熱河および興安地区 | 497 | ||
| 飯塚 浩二 | 戦争末期の蒙彊 | 514 | ||
| 飯沼 二郎 | アジア的農村社会の「近代化」の一事例 | 136 | ||
| 飯沼 二郎 | 日本農業生産力構造 | 468 | ||
| 飯沼 二郎 | 同時代人のみたフランス革命 | 470 | ||
| 飯沼 二郎 | 資本制大農経営の成立 | 475 | ||
| 飯沼 二郎 | マルクスの発展段階説における西洋と東洋 | 1330 | ||
| 飯沼,和正 | 個か全体か(上) | 1346 | ||
| いく | 生嶋 功 | マツバボタンの生長曲線の解析 | 593 | |
| 生嶋 功 | ウキクサ個体群の生長と密度効果 | 765 | ||
| 生嶋 功 | 琵琶湖の水生高等植物の現存量 | 1292 | ||
| いけ | 池田 源太 | 古代文化と吉野地域 | 770 | |
| 池田 徹太郎 | ロールシャッハテストのPattern analysis | 1044 | ||
| 池田 啓 | 香春岳における野生ニホンザル:Macacaf:fuscataの行動域と植生の関係 | 1396 | ||
| いさ | 井坂 由美子 | ヒトの新生児のいわゆる未熟さについての比較発達的研究 | 1409 | |
| 井坂 由美子 | ヒトの子どもの自然における位置:ポルトマンによるとみられるいわゆる特別未熟説批判 | 1556 | ||
| 伊沢 紘生 | 白山・蛇谷一円に生息する野生ニホンザルの生態学的調査:積雪期における群の遊動と群間関係について(その2) | 1394 | ||
| 伊澤 紘生 | ゲルディモンキーの生態:ボリビア・アクレ川予察行 | 1455 | ||
| 伊澤 紘生 | 新世界ザルの種間関係 | 1503 | ||
| 伊澤 紘生 | 北ボリビアの哺乳類について | 1575 | ||
| 伊澤 紘生 | 広鼻猿類の進化について:ティティの系統分類を中心に | 1576 | ||
| 伊澤 紘生 | Foods and feeding behavior of monkeys in the upper amazon basin | Y | 423 | |
| いし | 石 宙明 | 樺太・北海道蝶類採集記 | 128 | |
| 石 宙明 | 朝鮮東北地方産蝶類採集記録 | 282 | ||
| 石井 盛次 | マツ属植物の基礎造林学的研究 | 1078 | ||
| 石井 盛次 | 端の構造より区別せられたるハヒマツの諸型と其の分布(予報) | 1320 | ||
| 石川 栄吉 | 地理学と人類学の間 | 259 | ||
| 石川 栄吉 | 母系制より父系制へ | 271 | ||
| 石川 栄吉 | マルケサス原住民の婚姻と性規制 | 527 | ||
| 石毛 直道 | 日本稲作の系譜(下) | 415 | ||
| 石毛 直道 | 日本稲作の系譜(上) | 534 | ||
| 石城 謙吉 | 東北海道伊茶仁川に溯上したオショロコマについて | 883 | ||
| 石城 謙吉 | モズとアカモズのなわばり関係について | 1053 | ||
| 石城 謙吉 | 北海道のイワナ類とその保護の問題 | 1354 | ||
| 石田 晃 | 咬合力・咀嚼力および矯正力に対する頭蓋の力学的反応機構に関する実験的研究 | 1060 | ||
| 石田 英一郎 | 世界史と文化人数学 | 449 | ||
| 石田 英一郎 | 歴史民族学の限界 | 541 | ||
| 石田 英一郎 | 文化人類における比較:方法論的覚え書 | 1618 | ||
| 石田 文記 | 二つの自然と人間 | 741 | ||
| いず | 泉 末雄 | 雪の調査 第二号 | 1607 | |
| 泉 靖一 | 南アメリカの未開人ならびに古代の人びとの医術 | 1456 | ||
| 泉 靖一 | 「巫党来歴」考 | 1612 | ||
| いた | 伊谷 純一郎 | Twenty years with mount Takasaki monkeys | Y | 159 |
| 伊谷 純一郎 | Distribution and adaptation of chimpanzees in an arid area (Ugalla area wertern Tanzania) | Y | 160 | |
| 伊谷,純一郎 | 高崎山のニホンザル自然群における新しい食物の獲得と伝播 | 714 | ||
| 伊谷,純一郎 | ニホンザルの遊牧生活高崎山の群れについて | 767 | ||
| 伊谷,純一郎 | 霊長類の社会から人間の社会へ | 855 | ||
| 伊谷,純一郎 | アフリカの類人猿 | 1088 | ||
| 伊谷,純一郎 | イツりの森の物語 | 1089 | ||
| 伊谷,純一郎 | 洛北大鷺町周辺の動物 | 1144 | ||
| 伊谷,純一郎 | 霊長類の伝達機構 | 1553 | ||
| 伊谷,純一郎 | サルの言語と人類の言語 | 1589 | ||
| 伊谷,純一郎 | The society of Japanese monkeys | Y | 461 | |
| いち | 市原 | Photogeological survey of the siwalik ranges and terai plain southeastern Nepal | Y | 189 |
| いと | 伊藤 盛次 | 蚕卵内「ぐりこうげん」の形態学的研究 | 21 | |
| 伊藤 茂 | ローガン峰遠征報告 | 521 | ||
| 伊藤 茂 | イワナの漁法および加工法 | 678 | ||
| 伊藤 秀五郎 | 知性の辺境にたたずんで | 512 | ||
| 伊藤 忠夫 | Monboddoのof the origin and progress of languageについて(2) | 1632 | ||
| 伊藤 文男 | 赤石,木曾,下条山脈におけるトワダカワゲラの分布 | 1080 | ||
| 伊藤 正春 | 害虫発生予察理論について | 582 | ||
| 伊藤 正春 | 害虫個体群における行動の役割に関する実験的研究(第2報)コクヌストモドキの卵の分布様式 | 762 | ||
| 伊藤 正春 | コクヌストモドキ成虫の孔堀りご産卵 | 982 | ||
| 伊藤 正春 | 昆虫の集団生活の研究 | 1043 | ||
| 伊藤 正春 | 動物進化論再考:進化要因と進化過程の理論化 そして動物社会進化論の位置付け | 1160 | ||
| 伊藤 正春 | コクヌストモドキの実験個体群の増殖における'Air-space'の意義 | 1168 | ||
| 伊藤 正春 | 害虫の集合形成の機構に関する実験的研究 I:コクヌストモドキの集合度とくに周辺効果について | 1174 | ||
| 伊藤 正春 | 社会性昆虫の基本的特性 | 1326 | ||
| 伊藤 嘉昭 | Studies on the disoersal of leaf and planthopperts iii: an examination of the distance dispersal rate curves | Y | 191 | |
| 伊藤 嘉昭 | Fadtors that affect the fluctuations of animal numbers with special reference ot insect outbreaks | Y | 326 | |
| 伊藤 嘉昭 | Preliminary studies on the respiratory energy loss of a spider lycosa pseudoannulata | Y | 328 | |
| 伊藤 嘉昭 | Time requiered for settling of alate parthenogenetic viviparae of rhopaloosiphum maidis fitch on the barley plant | Y | 411 | |
| 伊藤 嘉昭 | 二足歩行と人間の進化 | 433 | ||
| 伊藤 嘉昭 | モンシロチョウ個体群の自然死亡率および死亡原因について | 614 | ||
| 伊藤 嘉昭 | 2種のアブラムシの混棲と葉の選択ならびにその生態学的意義について | 763 | ||
| 伊藤 嘉昭 | 生存競争をめぐる諸問題 | 776 | ||
| 伊藤 嘉昭 | ムギのアブラムシ類の寄主選択について | 965 | ||
| 伊藤 嘉昭 | ムギ類の混植および単植におけるアブラムシ3種の奇主選択 | 966 | ||
| 伊藤 嘉昭 | ムギのアブラムシ類の寄生植物について | 980 | ||
| 伊藤 嘉昭 | ムギのアブラムシ類のすみわけ構造に関する考察 | 981 | ||
| 伊藤 嘉昭 | 秋のハクサイ畑におけるヨトウムシ個体群の分散と死亡率 | 983 | ||
| 伊藤 嘉昭 | トンボの縄ばりと性行動 | 1162 | ||
| 伊藤 嘉昭 | 切れたポアソン分布 | 1288 | ||
| 伊藤 嘉昭 | 背番号つきのバッタを追う | 1298 | ||
| 伊藤 嘉昭 | ムギのアブラムシ類の増殖と移動 | 1300 | ||
| 伊藤 嘉昭 | アブラムシ数種の増殖型式 | 1301 | ||
| 伊藤 嘉昭 | 虫を放して虫を滅ぼす:不妊虫放飼法によるウリミバエの根絶 | 1382 | ||
| 伊藤 嘉昭 | 生活史の起原(1)(2):新しい生活史嶽のための覚書き | 1383 | ||
| 伊藤 嘉昭 | シオカラトンボの縄はり制 | 1459 | ||
| 伊藤 嘉昭 | 小林・巌の話題に対する討論講演 | 1471 | ||
| いな | 稲葉 左馬吉 | A preliminary note on the glochidia of Japanese freshwater mussels | Y | 255 |
| 稲葉 左馬吉 | Morphological and ecological studies on the glochidia larvae of the unionidae | Y | 292 | |
| 稲葉 左馬吉 | 基督教の経済理念 | 56 | ||
| 稲葉 左馬吉 | 長良川におけるアユの産卵から仔アユの降下まで V:卵の人口孵化の研究と仔アユについて | 1074 | ||
| 稲葉 左馬吉 | 長良川におけるアユの産卵から仔アユの降下まで VI:環境変化に対する仔アユの抵抗性,選好性,順応性 | 1075 | ||
| いぬ | 犬飼 哲夫 | A preliminary note on changes of mammalian fauna since the settlement of Hokkaido | Y | 420 |
| 犬飼 哲夫 | 笹の結実と野ネズミ | 1475 | ||
| いの | 井上 聡 | 冬期の河川におけるヤマメの生態 | 61 | |
| 井上 元男 | 北西部太平洋に於けるビンナガマグロ漁場動態に関する研究 1:漁獲水温より見た冬ビンナガの水温に対する適応性 | 766 | ||
| いま | 井街 譲 | レーベル氏病 | 662 | |
| 今村 学郎 | 1933年の地形学界の展望 | 119 | ||
| 今村 学郎 | 地形学界の展望 | 120 | ||
| 今村 学郎 | 砂の研究 | 278 | ||
| 今村 学郎 | 氷河と氷河地形 | 489 | ||
| 今村 学郎 | 日本高山地形研究(第6報)仙丈岳に於ける氷河地形の存在とその意義 | 1504 | ||
| 今村 豊 | 人類計測学30年 | 713 | ||
| 今村 豊 | 日本人の人類計測学的特徴 | 1316 | ||
| いわ | 岩城 操 | イメージ形成の地域特性4:北海道東藻琴の小学生にみられる北方系の優位性について | 1463 | |
| 岩城 操 | イメージ形成の地域特性3:北海道礼文島の小学生にられる北方系の優位性について | 1466 | ||
| 磐瀬 太郎 | 今西錦司・柴田篤弘著「生命相の類型的研究ー東亜の蝶を題材としてー」(1943-5)の原稿を読む | 54 | ||
| 岩田 悦行 | 山地傾斜地一般 | 668 | ||
| 岩田 悦行 | イチゴツナギ属(POA)植物の葉身の開閉と機動細胞 | 1057 | ||
| 岩田 久二雄 | beitrag zur kenntnis des gattung crabro fabricius aus Japan | Y | 10 | |
| 岩田 久二雄 | Biological notes on anoplius marginipennis yasumatsu | Y | 22 | |
| 岩田 久二雄 | Habits of four species of the Japanese hnging wasps that burrow in rotten wood | Y | 23 | |
| 岩田 久二雄 | Habits of a non-burrowing ammophila from Japan (a. aemulans kohl) | Y | 26 | |
| 岩田 久二雄 | Habits of some japanese pemphredonidds and crabronids | Y | 64 | |
| 岩田 久二雄 | Ecological notes on ceratina japonica cockrell | Y | 102 | |
| 岩田 久二雄 | Biology of homonotus iwatai yasumatsu | Y | 374 | |
| 岩田 久二雄 | 昆虫の食性に就ての雑録(1) | 3 | ||
| 岩田 久二雄 | 銀口蜂の造巣基と獲物に就いて | 275 | ||
| 岩田 久二雄 | 横這を狩るチビアナバチ1種の習性 | 301 | ||
| 岩田 久二雄 | 日本内地産葉切蜂六種の習性考察 | 363 | ||
| 岩田 久二雄 | 狩猟蜂と獲物の特殊関係 | 365 | ||
| 岩田 久二雄 | 台湾産数種の蜜蜂の習性(III) | 1188 | ||
| 岩田 久二雄 | 台湾産単独性狩猟蜂の習性(1) | 1216 | ||
| 岩田 久二雄 | 台湾産数種の蜜蜂の習性(II) | 1217 | ||
| 岩田 久二雄 | 台湾産数種の蜜蜂の習性 | 1218 | ||
| 岩田 慶冶 | 東南アジアのスシ | 260 | ||
| 岩田 慶冶 | タイ族における人生とその背景 | 448 | ||
| 岩田 慶冶 | 文化構造の生態学試論 | 529 | ||
| 岩田 慶冶 | 東南アジアの市場とその商品 | 562 | ||
| 岩田 慶冶 | 北部タイにおける稲作技術 | 571 | ||
| 岩田 慶冶 | 北部タイにおける村落社会の解体と再編成過程 | 1210 | ||
| 岩田 慶冶 | パ・タン村 | 1211 | ||
| 岩田 俊一 | 標識法によるヒメコガネ成虫の移動に関する研究 | 768 | ||
| 岩田 正俊 | The classification list of cestoidea in Japan | Y | 21 | |
| 岩田 正俊 | Ophiotaenia ranarum. A new amphibian cestode | Y | 304 | |
| 岩田 正俊 | Five new species of trichopterous larvae from Formosa | Y | 384 | |
| 岩田 正俊 | Trichopterous larvae frin Jaoan (IV) | Y | 385 | |
| 岩田 正俊 | 鴨川上流に於ける水棲昆虫 | 45 | ||
| 岩田 正俊 | 水棲昆虫採集保存及研究法 | 87 | ||
| 岩田 正俊 | 宮入貝ノ産地視察記(一) | 281 | ||
| 岩田 正俊 | 琵琶湖産鮎に寄生せる一條虫の学名に関する考察 | 291 | ||
| 岩田 正俊 | 京都市北郊鴨川上流の水棲昆虫 | 356 | ||
| 岩田 正俊 | 「マラリヤ」蚊(Anopheles)の採集及び保存法 | 368 | ||
| 岩田 正俊 | 日本産毛翅目幼虫科の検索表 | 539 | ||
| 岩田 正俊 | 日本産毛翅もく幼虫(第三報) | 642 | ||
| 岩田 正俊 | Diphyllobothrium mansonoides mueller とD. evinacei(Rudolphi)との形態比較 | 1190 | ||
| 岩田 正俊 | 大根島溶岩隧道内の動物相 | 1231 | ||
| 岩田 正俊 | 邦産既知種條虫類の分類 | 1232 | ||
| 岩田 正俊 | 宮入貝の産地視察記(二) | 1532 | ||
| 岩坪 昤子 | カラコラムの一寒村における歯科的調査 | 1404 | ||
| 岩村 忍 | ハザラ族の起源に関する諸問題 | 467 |
う
| 読み | 著者名 | 標題 | 和洋 | 配列番号 |
|---|---|---|---|---|
| うえ | 上木 泰男 | 奥越の鳥類相について(予報) | 1113 | |
| 上田, 明一 | エゾヤチネズミ研究史 | 1021 | ||
| 上田 弘一郎 | ヤツバキクヒムシによる被害に就て | 377 | ||
| 上田 正昭 | 折口学と芸能史 | 1378 | ||
| 上治 寅次郎 | ニュウカレドニヤ視察談 | 506 | ||
| 上塚 司 | 世界資源地としてのアマゾン | 498 | ||
| 上野 益三 | 秋吉台の地下水とその動物 | 204 | ||
| 上野 益三 | 台湾のPeltoperla | 205 | ||
| 上野 益三 | 蜉蝣の若虫とユスリカの幼虫 | 222 | ||
| 上野 益三 | 択捉島湖沼のプランクトン | 298 | ||
| 上野 益三 | 陸水生物学実習手引 | 490 | ||
| 上野 益三 | 北黒索温雨沿線に於ける吸血昆虫の調査 | 644 | ||
| 上野 益三 | 千島に於ける鰓脚類の分布 | 649 | ||
| 上野 益三 | 満州南部の枝角類 | 650 | ||
| 上野 益三 | 「動物と自然」への道を開いたひと | 827 | ||
| 上野 益三 | 川村先生 | 828 | ||
| 上野 益三 | 信濃の陸水とその生物 | 1344 | ||
| 上野 輝弥 | 大分県玖盆地さん新生代後期淡水魚類化石 | 865 | ||
| 上野 登 | ネパール雑感<トレッキングで感じたこと> | 1505 | ||
| 植松 辰美 | オランウータンの寝袋利用について | 60 | ||
| 植松 辰美 | 香川県下のマミズクラゲ | 1059 | ||
| 上松 和夫 | アマゴの海水飼育について | 892 | ||
| 植村 利夫 | 日本産オヒキグモの記載 | 931 | ||
| 上山 春平 | ブルジョワ革命と封建制 | 1279 | ||
| うす | 臼井 竹次郎 | Das kathchen von heilbronnの童話調 | 127 | |
| 臼井 竹次郎 | 運命の歌に言寄せて | 477 | ||
| 臼井 竹次郎 | わが遍歴の旅 | 478 | ||
| 臼渕 勇 | 弘前肉腫のMitomycin Cに対する耐性獲得機序 | 1572 | ||
| うち | 内田 俊郎 | Studies on experimental population of the azuki bean weevil callosobruchus chinensis | Y | 392 |
| 内田 俊郎 | 寄生と寄生蜂の相互作用系における固体数の長期変動 | 897 | ||
| 内田 俊郎 | 第2回シンポジウム I ニカメイチュウの発生消長 | 1224 | ||
| 内田 俊郎 | ヨツモンマメゾウムシに見られた相に似たニ型 第2報 | 1225 | ||
| 内田 俊郎 | 小豆象虫の棲息密度に関する実験的研究(2) | 1252 | ||
| うつ | 内海 冨士夫 | タイドプールの生態 | 595 | |
| うめ | 梅岡 義貴 | Goal-oriented group process in an operationally cibstrained situation (1) | Y | 353 |
| 梅岡 義貴 | 相互行動の分析法について(1) | 79 | ||
| 梅岡 義貴 | 相互行動の分析法について | 682 | ||
| 梅棹 忠夫 | 草刈るモンゴル | 149 | ||
| 梅棹 忠夫 | Datoga牧畜社会における家族と家畜群 | 632 | ||
| 梅棹 忠夫 | びわ湖環状水路公園地域計画 | 716 | ||
| 梅棹 忠夫 | 淡水魚群聚の構造1 | 901 | ||
| 梅棹 忠夫 | 生物社会関係の量的表現(1) | 947 | ||
| 梅棹 忠夫 | 生物社会関係の量的表現(2) | 989 | ||
| 梅棹 忠夫 | 北部大興安嶺の陸水 | 1038 | ||
| 梅棹 忠夫 | 固体間の社会的干渉 | 1046 | ||
| 梅棹 忠夫 | モンゴルの飲みものについて | 1531 | ||
| 梅棹 忠夫 | ローマ字の時代 | 1621 |
え
| 読み | 著者名 | 標題 | 和洋 | 配列番号 |
|---|---|---|---|---|
| えさ | 江崎 悌三 | Einige biologische beobachtungen uber die bienen und wespen mikronesiens | Y | 5 |
| 江崎 悌三 | A new tingitio from formosa | Y | 14 | |
| 江崎 悌三 | An undesctibed strepsipteron from Japan | Y | 15 | |
| 江崎 悌三 | New or unrecorded aquatic heteroptera from Japan and Saghalien | Y | 17 | |
| 江崎 悌三 | New henicocephalidae from Japan and Formosa | Y | 27 | |
| 江崎 悌三 | Die cicadiden-fauna der karolinen | Y | 31 | |
| 江崎 悌三 | A new species of scutelle rinae from Japan (Hamiptera: pentatomidae) | Y | 129 | |
| 江崎 悌三 | 九州帝国大学農学部農林省委託浮塵子駆除予防試験(報告第11) | 2 | ||
| 江崎 悌三 | 日本内地及び朝鮮より未記録のマツモムシ属2種に就いて | 100 | ||
| 江崎 悌三 | 台湾産蝶類分布記録 | 105 | ||
| 江崎 悌三 | 吐か喇群島の蝶類 | 106 | ||
| 江崎 悌三 | 九州帝国大学附属彦山生物学研究所要覧 | 122 | ||
| 江崎 悌三 | コノハテフの"擬態"問題 | 125 | ||
| 江崎 悌三 | 九州帝国大学農学部農林省委託浮塵駆除予防試験(報告第八) | 161 | ||
| 江崎 悌三 | 日本の現代昆虫学略史 | 162 | ||
| 江崎 悌三 | 北千島の蝶類 | 191 | ||
| 江崎 悌三 | 九州帝国大学農学部農林省委託浮塵子駆除予防試験報告・第12 | 214 | ||
| 江崎 悌三 | 人を刺すメクラガメの1種 | 230 | ||
| 江崎 悌三 | 紀伊・大和地方の特殊動物相 | 232 | ||
| 江崎 悌三 | 京都「昆虫学雑誌」発刊当時の秘話 | 303 | ||
| 江崎 悌三 | 日本に於けるTanyderidaeの発見 | 304 | ||
| 江崎 悌三 | 浮塵子の敵虫に就いて | 318 | ||
| 江崎 悌三 | 少年は語る | 329 | ||
| 江崎 悌三 | 北大東島の昆虫記録(第一報) | 333 | ||
| 江崎 悌三 | 盛岡の昆虫記 | 335 | ||
| 江崎 悌三 | 九州帝国大学農学部農林省委託浮塵子駆除予防試験(報告・第十) | 339 | ||
| 江崎 悌三 | 九州帝国大学農学部農林省委託浮塵子駆除予防試験(報告・第七) | 341 | ||
| 江崎 悌三 | 九州帝国大学農学部農林省委託浮塵子駆除予防試験(報告・第三) | 342 | ||
| 江崎 悌三 | 九州帝国大学農学部農林省委託浮塵子駆除予防試験(報告・第四) | 343 | ||
| 江崎 悌三 | 九州及び琉球昆虫目録第1輯 | 344 | ||
| 江崎 悌三 | 九州帝国大学農学部農林省委託浮塵子駆除予防試験(報告・第九) | 358 | ||
| 江崎 悌三 | 「北海道蝗害報告書」について | 371 | ||
| 江崎 悌三 | 人形石の説 | 376 | ||
| 江崎 悌三 | ニ三双翅目に見る日本及び北アメリカ間の特異なる分布型とその起源 | 803 | ||
| 江崎 悌三 | 昆虫の分布より見たる九州 | 843 | ||
| 江崎 悌三 | 福岡県に於て注意すべき蝉 | 1362 | ||
| 江崎 悌三 | 八重山諸島昆虫採集記 | 1425 | ||
| 江崎 悌三 | 生物の学名の読み方 | 1436 | ||
| 江崎 悌三 | 動物分類学の現状 | 1437 | ||
| 江崎 悌三 | 生物の学名の読み方[補遺] | 1444 | ||
| 江崎 悌三 | 列車運転を妨害する倍脚類 | 1449 | ||
| えは | 江畑 魁 | 空間識喪失:spetial disorientation 第1編.分類並びに体験例の生理学的考察 | 673 | |
| 江畑 魁 | ジェット機による閉眼飛行の経過及びその持続時間の観察実験 | 674 | ||
| 江畑 魁 | 空間識喪失:spetial disorientation 第2編.統計的観察 操縦えの影響並びに訓練による克服性について | 675 | ||
| 江原 昭善 | Methodisches zum prognathie problem beim morphologischen vergleich von primatenschadeln | Y | 161 | |
| 江原 昭善 | 人類を表現する諸用語とその概念について | 1008 | ||
| 江原 昭善 | 霊長類学の人類学への寄与 | 1009 | ||
| 江原 昭善 | 霊長類シリーズ 6:形態 | 1097 | ||
| 江原 昭善 | 初期人類の形態特徴とその適応的意義 | 1148 | ||
| 江原 昭善 | 霊長類学への展望:霊長類学と系統研究 | 1555 | ||
| 江原 昭善 | 猿人類の起源と系統をめぐって | 1562 | ||
| 江原 昭善 | オナガザル類のルーツを求めて | 1563 | ||
| える | エルトン C.S. | 動物の生態学 | 1391 | |
| えん | 遠藤 誠道 | 吉林省舒蘭炭田及び奉天撫順炭田参化石 | 1185 | |
| 遠藤 匡俊 | アイヌの移動と居住集団:江戸末期の東蝦夷地を例に | 1519 | ||
| 遠藤 匡俊 | 江戸末期の三石アイヌにおける流動的集団の形成メカニズム | 1526 |
お
| 読み | 著者名 | 標題 | 和洋 | 配列番号 |
|---|---|---|---|---|
| おう | 近江 | Plantae novae uaponicae (IV) | Y | 107 |
| おお | 大内 幸雄 | 日出雲林業の展開 | 715 | |
| 大内 ヨシオ | A new soothsayer from eastern China | Y | 305 | |
| 大内 ヨシオ | Notes on some flies of genus fannia from eastern China | Y | 306 | |
| 大内 ヨシオ | a new murcoid fly from south China | Y | 307 | |
| 大内 ヨシオ | on some cyrtid flies eastern China and a new species from formosa | Y | 308 | |
| 大内 ヨシオ | Contributiones ad cognitionem insectrum asiae orientalis iv | Y | 316 | |
| 大内 ヨシオ | contributiones ad cognitionem insectrum asiae orientalis iii | Y | 318 | |
| 大垣,昌弘 | ユスリカ幼虫の造巣行動 | 948 | ||
| 大串 龍一 | 今西学派の系譜:いわゆる今西学説の発展をめぐる一考察 | 1408 | ||
| 大杉 繁 | 北蒙古連盟及び中支地方の土壌に就て | 1416 | ||
| 太田 哲 | 主として宮城県下に於ける暖帯林樹種の分布と気象要因との関連性について | 972 | ||
| 太田 喜久雄 | 九州の戦略地理学的意義 | 240 | ||
| 太田 喜久雄 | 支那文献に表れた白頭山 | 555 | ||
| 太田 喜久雄 | 咸豊五年北流後に於ける黄河河口の歴史地理学的研究 | 558 | ||
| 太田 喜久雄 | 「中華民国及満州広域図」製作過程に就て | 1328 | ||
| 太田 嘉四夫 | 北海道林業における野鼠害防除技術の問題点 | 88 | ||
| 太田 嘉四夫 | 哺乳類の生活 | 712 | ||
| 太田 嘉四夫 | なわばり制と順位制 | 917 | ||
| 太田 嘉四夫 | 林業生産の特質について | 1368 | ||
| 太田 嘉四夫 | 北海道に於ける林木鼠害とその防除 | 1432 | ||
| 大竹 昭郎 | 生態的地位を等しくする2種類の動物個体群の野外での共存について | 888 | ||
| 大塚 外次 | 屋久島産積翅目23 | 207 | ||
| 大塚 外次 | 屋久島産積翅目23 | 208 | ||
| 大塚 外次 | 廣島地方の蜉蝣目若虫 | 850 | ||
| 大平 仁夫 | 木曽御岳山のコメツキムシについて | 679 | ||
| 大森 南三郎 | Experimental studies on the cohabitation and crossing of two species of bedbug cimex lectularius l. and c. hemipterus f. | Y | 309 | |
| 大森 南三郎 | デング熱伝播蚊の生態と其の駆除 | 414 | ||
| 大森 南三郎 | 台北市内で人類を襲ふ蚤類に就て | 416 | ||
| 大森 南三郎 | デング熱の予防対策 | 538 | ||
| 大森 南三郎 | 家*二依る再帰熱病原体ノ伝搬実験 | 604 | ||
| 大森 南三郎 | 瀬戸四双島夜間採集に就いて | 639 | ||
| 大森 南三郎 | とこじらみ(Cimex lectularius Linnaeus)ノ生育ニ及ボス低温ノ影響(第一報)低温0℃ノ影響ニ就テ | 1191 | ||
| 大森 南三郎 | たいわんとこじらみ(Cimex hemipterus fabricius)ノ生育ニ及ボス低温ノ影響(第四報)低温0℃ノ影響ニ就テ | 1192 | ||
| 大森 南三郎 | 「イへダニ」ニ関スル研究(第三報) 「イへダニ」ノ生態ト其ノ駆除 | 1193 | ||
| おか | 岡 ナオミチ | Experimental studies on visual pattern discrimination in the varied tit (parus vatius varius) - with special referrence to the limit of its discriminative ability with geometrical figures | Y | 418 |
| 岡 正雄 | 第4回国際人類学・民族学会議に出席して(学術情報no.1) | 1117 | ||
| 岡市 友利 | カワハギおよびアミメハギの体色変化 | 607 | ||
| 岡崎,勝太郎 | 二化螟虫の大発生と稲田微細気象について | 961 | ||
| 岡崎,勝太郎 | イネハモグリバエの防除に関する研究(第1報) | 962 | ||
| 岡崎,勝太郎 | イネハモグリバエの防除に関する研究(第2報) | 971 | ||
| 岡崎 敬 | オーレル・スタイン | 408 | ||
| 岡崎 敬 | タキシラよりスーサまで | 1350 | ||
| 緒方 洪平 | 世界気候ノ衛生学的研究 第一扁 | 41 | ||
| 岡田 イチジ | Journal of the faculty of agriculture | Y | 320 | |
| 岡田 弥一郎 | Notes on the boreal animals in Honsyu Japan | Y | 421 | |
| 岡田 弥一郎 | 欧州における養鱒事情 | 270 | ||
| 岡田 弥一郎 | 日本におけるタニシの研究 | 598 | ||
| 岡田 弥一郎 | 東亜のモクヅガニに就きて | 787 | ||
| 岡田 弥一郎 | カハシンジュガヒの分布に就きて | 848 | ||
| 岡田 喜一 | the desmidflora of the northern Kurile islands | Y | 323 | |
| 岡田 喜一 | 北千島概観 | 195 | ||
| 岡本 | Piedmont glaciation in the taiga forests of ice ages in Japan and northern Italy similar to those now present in southern Alaska | Y | 156 | |
| 岡本 慶文 | 氷期日本の確かな低位氷河遺跡の新発見と山砂利層及び寒帯系・高山系動植物の南下 | 1430 | ||
| 岡本 省吾 | 和歌山演習林植物誌 | 1139 | ||
| 岡本 慶文 | 擦痕礫をふくむ山砂利層の分布と日本の低位氷河作用 | 1101 | ||
| 岡本 慶文 | 北半球の第四紀氷河前線と樹木限界線生物群の相伴的南下と日本の低位氷河 | 1104 | ||
| 岡本 慶文 | 氷河日本の確かな低位氷河遺跡の新発見と山砂利層及び寒帯系・高山系植物の南下 | 1105 | ||
| 岡本 慶文 | 中新世の天変地変と油田及び生物相の変動 | 1147 | ||
| 岡本 慶文 | 極楽寺山山頂の古第四期の氷河礫層 | 1347 | ||
| 岡山 俊雄 | 本邦氷河問題研究拾遺 | 435 | ||
| 小川 琢治 | 日本に於ける氷河作用の意義 | 114 | ||
| 小川 琢治 | 氷河作用と氷成層系 | 483 | ||
| 小川 琢治 | 中央日本氷成堆積物の分布(二) | 484 | ||
| 小川 琢治 | 中央日本氷成堆積物の分布(一) | 485 | ||
| 小川 琢治 | 中央日本の洪積世氷河作用に就いて(三 四) | 486 | ||
| 小川 琢治 | 中央日本の洪積世氷河作用に就いて(一 二) | 487 | ||
| 小川 琢治 | 日本の氷河時代に関する問題と其の研究法 | 488 | ||
| おく | 奥川 一之助 | 京都府巨椋干拓農地に繁殖するケリ(チドリ科)の生態調査資料 | 710 | |
| 奥川 一之助 | 巨椋干拓地(京都府)の野鳥 | 711 | ||
| 奥田 重俊 | 自然教育園の植生と現存植生図 | 1033 | ||
| 奥平 | ラオス問題について | 469 | ||
| 奥富 清 | 向宇品における森林植生の連続構造 | 610 | ||
| 奥野 良之助 | observations and discussions on the social behaviors of marine fishes | Y | 274 | |
| 奥野 良之助 | ニザダイの群れ行動 | 1283 | ||
| 奥村 テイイチ | Einige aufzeihnungen uber die epiophlebia superstes selys | Y | 365 | |
| おた | 織田 武雄 | イランの農業 | 146 | |
| おの | 小野 勇一 | チゴガニの固体間の相互関係 | 916 | |
| 小野 勇一 | 祖母・傾山系におけるカモシカ二次林の利用度について | 1401 | ||
| 小野 嘉明 | Sequence of the mating activities in oryzias latipes | Y | 187 | |
| 小野 嘉明 | Experimental analysis of the sigh stinuli in the mating behaviour in oryzias latipes | Y | 188 | |
| 小野 嘉明 | One observation on the social dominance status in hens | Y | 240 | |
| 小野 嘉明 | Orang-Utanの"文字"による行達行動1:数字の学習実験(3) | 699 | ||
| 小野 嘉明 | Orang-utanの文字による伝達行動 I: 数学の学習実験(1) | 1106 | ||
| 小野 嘉明 | Orang-utanの文字による伝達行動 I: 数学の学習実験(2) | 1107 | ||
| 小野木 三郎 | 各務原市及び御岳嶽山における帰植物の生態 | 1381 | ||
| 小野木 三郎 | 学芸活動実践論 | 1384 | ||
| 小野木 三郎 | 岐阜県朝日村青屋川流域の草地植物群落 | 1385 | ||
| 小野木 三郎 | ぼくの博物館日記 | 1614 | ||
| おは | 小原 秀雄 | ホミニゼーションケンキュウの現代的意義 | 1453 | |
| 小原 秀雄 | 今西錦司氏における「生物の世界」 | 1579 | ||
| 小原 秀雄 | 人間の生活と動物の生活 | 1602 | ||
| 小原 秀雄 | 人間の生活と動物の生活 | 1606 | ||
| おも | 尾本 ケイイチ | The distribution of polymorphic traits in the Hidka Ainu | Y | 272 |